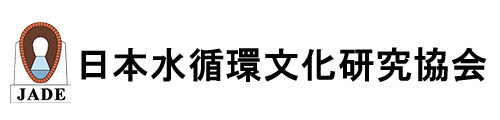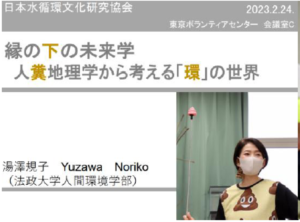《縁の下の未来学-人糞地理学から考える「環」の世界》講演録
2023年2月24日(金)18:30~20:30、東京ボランティア・市民活動センターにて開催いたしました下記の講演会の講演録を当日配布されたハンドアウト資料と併せて掲載します。 講師:法政大学人間環境学部 湯澤規子教授 […]
「水循環情報ボックス」
これまでの「水循環情報ボックス」の中身はこちらです。「水循環教材」のコンテンツを含めています。 日本水循環文化研究協会では、水循環に関するさまざまな情報を収集していきたいと思っております。会員諸兄姉をはじめ関係する皆様か […]
第2回水循環文化研究発表会の開催について
第2回水循環文化研究発表会を以下の要領で開催いたしますので、ふるって応募いただきたいと思います。なお、当日午前中は、同会場で、当協会の定例総会ならびに2024年度・水道行政の国土交通省移管に関連して、元厚生省水道環境部長 […]
2023年度定例総会開催のお知らせ
特定非営利活動法人 日本水循環文化研究協会 定例総会開催ならびに講演会のご案内 下記の通り、改組・改称後初めての定例総会を開催いたします。定款を改正いたしましたので、リモート参加、電子媒体での出欠届、委任状提出が可能にな […]
水力発電開発と「水返せ運動」
1960年、大井川中流部に塩郷堰堤が完成、導水管による下流川口発電所への送水を開始した。以降、堰堤から川口発電所(約20km)区間では夏の河原砂漠・冬の砂嵐、河床低下を引き起こした。さらに堰堤上流部では土砂の堆積と河床の […]
『都市の医師―濱野弥四郎の軌跡』翻訳への思い
本会前代表・稲場紀久雄先生が執筆された「都市の医師ー浜野弥四郎の軌跡」が台湾版が出版されたことについては、ホームぺ時でも紹介いたしました(1月24日)が、翻訳者の鄧淑晶、鄧淑瑩ご姉妹より、翻訳への思いを寄稿していただきま […]
水循環教材の構成(暫定)
水循環教材構成案 はじめに 第1章 水循環とその恵沢 1.水の価値・水の恵沢 2.私たちのくらしと水循環 第2章 水循環とその変容 1.近代化と水循環の変容 2.水循環と源流域 3.水循環の変容は何をもたらすのか:都市化 […]